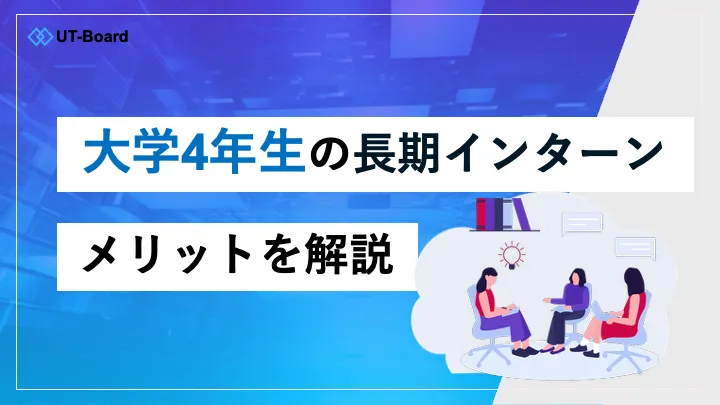長期インターンの雇用形態とは?扶養についても詳しく解説

長期インターンの雇用形態として、どのようなものがあるのでしょうか?
アルバイトや正社員とどう違うのか、気になりますよね。
結論、長期インターンの雇用形態は主に「非正規社員」と「業務委託契約」の2つです。
雇用形態によって、給与の支払われる仕組みが異なるため、始めるためにきちんと理解しておくことが重要です。
本記事では、二つの雇用形態の概要だけでなく、長期インターン未経験者がチェックしておくべきこと、そして長期インターン中の保険、税金関係などについて、現役東大生が詳しく解説しています!
気になる方はぜひチェックしておきましょう!
目次
長期インターンの雇用形態は主に2種類 雇用契約上の非正規社員(アルバイトと同じ) 雇用契約による長期インターンの注意点 業務委託契約 業務委託による長期インターンの注意点 長期インターン中の扶養・保険について 雇用保険 社会保険 労災保険 長期インターンの雇用形態に関するQ&A Q. 長期インターンの給料で103万を超えたら扶養から外れますか? Q. 長期インターンは年末調整・確定申告は必要ですか? まとめ長期インターンの雇用形態は主に2種類

長期インターンの雇用形態は、主に以下の2種類です!
- 非正規社員
- 業務委託契約
長期インターンの契約は基本的に上記2つが主です。
契約別の注意点も詳しく解説しますので、ぜひ長期インターンの雇用形態について知りたい方は最後まで読みましょう!
雇用契約上の非正規社員(アルバイトと同じ)
長期インターンの一つの雇用形態として、雇用契約上の「非正規社員」があります。
非正規社員の契約では、インターン生は正式な社員とは異なり、アルバイトに近い形で働くことになります。
通常のアルバイトと同様に、労働時間や勤務条件が比較的柔軟に設定されることが多く、インターンにとっては学業や他の活動との両立がしやすいです。
また、非正規社員の契約では、給与は時給や日給で計算されることが一般的です。
長期インターンとアルバイトに関する違いを徹底比較した記事も是非参考にしてください!
雇用契約による長期インターンの注意点
雇用契約による長期インターンの注意点は以下の2つです。
- 最低賃金が定められている
- 社会保険への加入義務が発生する場合がある
上記2つについて詳しく解説していきます。
1.最低賃金が定められている
雇用契約を結んだときの最低賃金は「最低賃金法」(参考:厚生労働省HP)という法律で定められています。学生の身分で長期インターン生であっても最低賃金未満の時給で働かせることは法律に違反しています。
長期インターン生として雇用契約を結ぶ際には、必ず最低賃金を下回っていないか確認するようにしましょう。
もし、下回っている場合は必ず応募を取りやめるようにしましょう。
2.社会保険への加入義務が発生する場合がある
一般的に、社会保険への加入義務が発生するのは、年収が130万円以上の場合です。
長期インターンに参加するために大学を休学してフルタイムで働こうと考えている学生は注意が必要です。
後ほど社会保険に関して詳しく解説しますので、その部分を参考にしてください。
業務委託契約
長期インターンのもう一つの雇用形態は、「業務委託契約」です。
業務委託契約では、インターン生は企業との間で特定の業務を行うことを約束し、その対価として報酬を受け取ります。
つまり、非正規社員は業務時間に応じて給与が支払われるのに対して、業務委託契約では、業務で完成させた成果物に対して対価が支払われる、といったイメージです。
例えば、ライター職の長期インターンシップでは、この業務委託契約がよく用いられます。
ライターのインターン生は、特定のテーマや内容に基づく記事の執筆を委託され、その作成した記事のクオリティや執筆数に応じて報酬を受け取ります。
業務委託契約の形態では、非正規雇用よりもさらに柔軟な働き方ができます。
労働時間や働き方に関する柔軟性が高く、インターン生自身が業務のスケジュールを調整することが可能です。
ただし、業務委託契約は完成物に対して報酬が支払われるため、請け負った仕事にかかった時間に対して、成果物・納品物の報酬が少ないと、時給換算すると割に合わない仕事になる可能性もあります。
自分の能力次第で、時給が高くなる場合も低くなる場合もあることは頭に留めておいた方が良いでしょう。
業務委託による長期インターンの注意点
業務委託による長期インターンの注意点は以下の2つです。
- 労働量に対しての報酬が最低賃金以下になる可能性もある
- 研修が充実していないことが多い
上記2つについて詳しく解説していきます。
労働量に対しての報酬が最低賃金以下になる可能性もある
「業務委託契約」の場合だと、業務そのものや請け負った仕事の成果物・納品物が対価の基準となります。
そのため、非常に多くの時間を費やしても、時給換算で見た場合に報酬が低くなるケースがあります。
一方で、非正規社員契約(アルバイトと同じ)の場合、働いた時間に対する報酬が支払われるため、労働の対価が明確です。
研修が充実していないことが多い
業務委託契約の場合、研修が充実していないことが多く、未経験者が必要なサポートを受けられない可能性が高いです。
業務委託契約では基本的に任された仕事を各自のペースでこなしていくことが求められます。
企業側も業務委託で契約する場合は研修などを想定していないことが多く、業務が丸投げされるケースもあり、必要な指導や支援を得られずに困難な状況に陥るリスクがあります。
長期インターンは、実務経験を積む絶好の機会ですが、未経験者は特に雇用形態のチェックを怠らないようにしましょう。
長期インターン中の扶養・保険について

長期インターン中に適用される保険は、主に以下の3つです。
- 雇用保険
- 社会保険
- 労災保険
以下、詳細に説明していきます!
雇用保険
雇用保険は、雇用の安定や就職の促進を目的とした保険です。
労働者が安定して働けるように失業時や休業時のサポートが目的となるため、基本的に学生は適用されません。
しかし、以下のケースなどでは雇用保険が適用されます。
- 卒業後もインターン先の企業で雇用予定の学生
- 休学中の学生
- 夜間学部の学生
これはあくまで例外的なケースなので、自分は雇用保険が適用されないか、あらかじめチェックしておくと良いでしょう!
社会保険
長期インターンとして働く際、特に注意すべきなのが、社会保険への加入に関する規定です。
社会保険とは、病気や怪我(けが)によって生活に困った人を社会政策的に救うための保険制度のことです。
一般的に、社会保険への加入義務が発生するのは、年収が130万円以上の場合です。
そのため、長期インターンでバリバリ働いて稼いでいる人は、社会保険への加入が必要となるケースが多いと言えるでしょう。
社会保険には健康保険や厚生年金保険が含まれ、これらは労働者の健康や将来の年金受給にあてられます。
このため、長期インターンとして相応の収入を得ている場合は、社会保険に加入することで、医療費の補助や将来の年金受給資格を得ることも可能となります。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中に発生した事故や病気に対して保障を提供します。
具体的には、労働者が業務の遂行中に負傷したり、業務に起因する疾病に罹患したりした場合に、治療費の補償や休業補償などの給付を受けることが可能です!
また、通勤途中の事故も労災保険の対象となることがあります。
長期インターンで雇用契約を結ぶ場合、労災保険が適用されることが一般的です。
この保険が適用されるためには、長期インターンとしての雇用契約が正式に存在する必要があるので、インターンを始める前に、雇用先の企業との契約を明確に確認しておくことが重要です。
また、保険の詳細内容や適用範囲についても、事前に理解しておくと良いでしょう!
長期インターンの雇用形態に関するQ&A

最後に、長期インターンの雇用形態に関して、よくあるQ&Aを解説します!
長期インターンの給料で103万を超えたら扶養から外れますか?
長期インターンの給料で103万円を超えたら、扶養から外れてしまいます。
アルバイトと同様に、給与が103万円を超えると税法上の扶養家族の要件を満たさなくなるため、家族の税負担の増加や社会保険料、所得税の支払い義務などが発生します。
長期インターン生として年間103万円以上の給与を受け取る場合は、親と相談し、これ以上続けるかどうかの判断をすると良いでしょう!
長期インターンは年末調整・確定申告は必要ですか?
長期インターンとして働いている場合、確定申告が必要になるのは以下のような特定の状況に該当したときです。
1. 年間103万円以上の給与を得た場合:
収入が103万円を超えると、扶養控除の対象外となり、所得税の申告が必要です。
所得が多いほど税負担が増えるため、正確な申告が必要になります。
2. 2か所以上でアルバイトやインターンをしており、サブの雇用先での給与所得が年間20万円を超える場合:
複数の雇用先からの給与所得がある場合、主たる雇用先以外の収入が20万円を超えると、それらの収入について確定申告が必要になります。
3. 株やアフィリエイトなど、副業の所得が年間20万円を超える場合:
また、給与所得以外の収入(副業や投資など)が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
給与所得がない場合の所得の基準は38万円以上です。
4. 年の途中で退職した後、働いていないなど年末調整を行なっていない場合:
年末調整は通常、勤務先で行われますが、年の途中で退職して別の職に就いていない場合など、年末調整が行われていない状況では確定申告が必要です。
これらのケースに当てはまる場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告のメリットは、過去に過払いした税金の還付などです。
源泉徴収された税金が、実際の税負担額より多い場合、差額が戻ってきたりします。
必要なときは、税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう!
まとめ

いかがでしたでしょうか?
長期インターンでは、複数の雇用形態があり、雇用形態によって支払われる給与の仕組みが異なります。
先ほども言いましたが、業務に慣れていない学生は非正規雇用として、しっかり企業に面倒を見てもらうことをおすすめします。
雇用形態の仕組みを理解し、次の長期インターンのステップに進みましょう!